お供えとは、亡くなった人やご先祖さま、神さま仏さまに捧げる品物や食べ物のことです。
お供え物には日持ちがする食べ物がよいので、乾物はお供えに適した品と言えるでしょう。
ただし、神式と仏式では死後の考え方に違いがあるため、お供えする乾物の選び方にはマナーがあります。
神式のお供えには海の幸の「昆布」や山の幸の「干ししいたけ」、仏式のお供えには小分けできる「フリーズドライのお味噌汁」や「焼き海苔」などの乾物がおすすめです。
この記事ではお供えに乾物を選ぶときのマナーや、お供えののしの種類や書き方、お供えをいただいたときのお返しについて解説します。
お供え選びのマナーを知って、故人やご先祖さまはもちろん、遺族の方にも喜ばれるお供えの品を選びたいですね。
お供え物に乾物を選ぶポイント

お供えには2つの意味があります。1つは亡くなった人を偲び感謝の気持ちを込めること。
神式と仏式では死後の考え方に違いがあることから、それぞれにふさわしいお供えの選び方があります。
お供えのもう1つの意味は、故人を偲ぶ機会を作ってくれた遺族への感謝の意を表すことです。
神式のお供えには海の幸の「昆布」や山の幸の「干ししいたけ」、仏式のお供えには小分けできる「フリーズドライのお味噌汁」や「焼き海苔」などの乾物がおすすめです。
なお、キリスト教には品物や食べ物をお供えする習慣がありません。葬儀や墓前にお供えしたいときはお花をお供えしましょう。
ここでは神式、仏式それぞれのお供えにふさわしい乾物について詳しく解説していきます。
神式のお供え
神式では、人が亡くなると氏神となって子孫を守るとされています。
お供えは神さまへの捧げ物で、神さまに献上する食べ物を神饌(しんせん)といいます。
- 神饌(しんせん)とは
水、米、塩の3つを基本とし、お餅、お酒、海の幸、山の幸、お菓子などをお供えします。
神さまへのお供え物として乾物を選ぶとき、海の幸は昆布やひじきなど、山の幸は干ししいたけや高野豆腐などがよいでしょう。
神事がすべて終わったあと、お供え物を下げて食べる「直会(なおらい)」という習慣があります。
お供え物には神さまのおちからがこもり、お供え物を食べることは神さまと食をともにして神さまと一体になるとされるからです。
お供え物として乾物を選ぶときのポイントをまとめましたので参考にしてみてください。
- 海の幸…昆布、ひじき、海苔、寒天など。
- 山の幸…干ししいたけ、高野豆腐、切り干し大根など。
- 日本の神さまへの捧げ物なのでできるだけ国産や、地元の食材を選びましょう。
- 神さまへの捧げ物ですので見た目も大事。特売、値引きなどの札がついたものは避けましょう。
仏式のお供え
仏式では、人が亡くなると魂となり、四十九日で成仏し仏さまになると考えられています。
お供えは亡くなった人の魂を供養し、仏さまに感謝を伝えるための物です。
仏式の供養には五供(ごく)と呼ばれるお供え物を基本とし、仏前に供えて亡くなった人の魂が安らかであるよう祈ります。
- 五供(ごく)とは
香、花、灯燭(とうしょく)、浄水、飲食(おんじき)の5つです。
香はお線香、灯燭(とうしょく)はロウソク、飲食(おんじき)は炊いた白いご飯のことです。
仏前にお供えしたあとの飲食(おんじき)は下げて家族がいただきます。
仏さまにお供えした物を食べることは亡くなった人やご先祖さまと食べ物を分け合うことになり、供養の一環だからです。
私の実家にもお仏壇がありました。私のおばあちゃんはお菓子や果物などいただき物があると、先に仏さまにとお仏壇にお供えしてから食べていたのを覚えています。

私のおばあちゃんがお仏壇のお供え物を「仏さまのごく」って言ってたな。
「五供(ごく)」のことだったんだ!
仏式のお供え物を選ぶとき、ふさわしいとされるポイントは次の3つです。
- 消え物…使用したり、食べたりしてなくなる物。悲しいことが消えてなくなるよう祈るため。
- 小分けされている物…仏前にお供えした品物は仏事が終わった後に配ることが多く、小分けされていると配りやすいため。
- 日持ちがする物…たくさんお供え物があっても、日持ちがする物なら遺族の方がゆっくりと消費することができるので困らないため。
乾物は食べ物なので消え物にあたり、日持ちもしますのでお供え物にふさわしいと言えるでしょう。
「フリーズドライのお味噌汁」や「焼き海苔」は軽くてかさばらず、配るときに衛生的で遺族の方にも喜ばれるでしょう。
ただし、仏式のお供えには避けた方が良い乾物もあります。避けるべきポイントは次の3つです。
- 縁起物…昆布やかつお節はお祝いごとに用いられるため、悲しみごとのお供えにはふさわしいくないとされます。
- 殺生につながる物…肉や魚はもちろん、肉や魚由来の材料が使われていたり、包装などに動物柄が印刷されていたりする物も避けましょう。
- 日常的に使わない物…普段あまり乾物を使用しない方に干ししいたけや切り干し大根などの乾物を差し上げるのは迷惑かもしれません。

関東では海苔はふつう「焼き海苔」だけど、関西では「味付け海苔」が一般的なんだって。

同じ海苔でも地域によって好まれる物が違うのね。

お供え物選びに迷ったら周囲の人に相談してみるのも良い方法だね。
お供えののしは種類と書き方をおさえよう

お供え物には「のし紙」でなく「掛け紙」を使い、表書きは「御供物」、のし掛けは外掛けにするのが一般的です。
お供え物ののし紙の種類や表書きの書き方にはマナーがあります。
のし紙は本来お祝いごとに使うものであり、仏さまにはなま物をお供えしてはいけないので、なま物を表すのし紙は使いません。
お供え物にはのし紙ではなく水引だけを印刷した「掛け紙」を掛けますが、お供え物に掛け紙を掛けることも「のし紙を掛ける」と言うのがふつうです。
ここからは、慶事に使われるのし紙と区別するため、弔事ののし紙と言うことにします。
弔事ののし紙や表書きの書き方に迷うときは、周囲の人やお店の人に相談するとよいでしょう。
お悔みの場面での弔事ののし紙の使い方をおさえて、失礼のないようにお供え物を準備しましょう。
弔事ののし紙の種類
- のし紙とは
かしこまった場面での贈り物を渡すときには、通常の包装のほかにのし紙を掛けます。
「のし」とはもともとはあわび貝を薄くのして干した物。
のしを包装の上から右肩に貼ることでなま物であることを意味します。水引とのしを印刷した紙がのし紙です。
お供え物には「のし紙」ではなく水引だけを印刷した弔事ののし紙である「掛け紙」を掛けます。
弔事ののし紙で蓮の花が印刷されている物があります。蓮の花は仏教とのかかわりが深く、他の宗教では用いられません。
神式も仏式の弔事ののし紙と同じ物でかまいませんが、無地を選びましょう。
- 水引
水引は贈答品に掛ける飾りひものことで、水引の色と数、結び方で用途が分かれます。
水引には3つの意味があるといいます。1つ目は未開封であることを示す意味。2つ目は魔除けの意味。3つ目はひもをひいて結ぶことから人と人とを結びつける意味です。
弔事ののし紙は、水引の数は4本、結び方は結び切りが基本です。
結び切りは一度結んだらほどけない結び方。悲しみごとは「1度きり」で「繰り返さない」ことを意味します。
弔事には、白黒、双銀、黄白の水引が使われ、お供え物をお渡しするタイミングで水引の色を使い分けます。一般的な使い方は下記の表を参考にしてみてください。
| お供え物を渡すタイミング | 弔事ののし紙 |
|---|---|
| 四十九日前(お通夜・葬儀) | 水引は白黒の結び切り |
| 四十九日以降(各種法要) | 水引は白黒、双銀、黄白のいずれかの結び切り |
| お盆 | 水引は黄白の結び切り |
ただし、地域によっては弔事ののし紙の使い方が異なる場合があります。事前に周囲の人に確認しておくと良いでしょう。
- 弔事ののし紙の掛け方
包装紙の上からのし紙を掛けることを「外掛け」、包装紙の内側にのし紙を掛けることを「内掛け」と言います。
お供え物を贈るとき、外掛けと内掛けどちらにするか迷うところですが、結論はどちらでもOK。
外掛けにするメリットは、どなたからのいただき物かがはっきりとわかること。
内掛けはのし紙が外側から見えないため、上品な印象をあたえます。
お供え物を贈るときは遺族の方にわかりやすいよう外掛けにするのがおすすめです。
弔事ののし紙の書き方
- 表書きの文言
弔事ののし紙には、水引の上中央に表書きを書きます。表書きの文言はお供え物を贈るタイミングにより変えましょう。
一般的には下記の表を参考にしてみてください。迷うときは「御供物」にしておくと失礼がないでしょう。
| 表書きの種類 | お供え物を贈るタイミング |
|---|---|
| 御霊前 | 四十九日前のときに使う表書き。神式のお供えでも使えます。 |
| 御仏前 | 四十九日以降に使う表書き。 ただし、浄土真宗では亡くなった後すぐに仏さまになると考えられているため、四十九日前でも表書きは御仏前を使います。 |
| 御供物 | 時期を選ばずに使える表書き。地域によっては「御供」と書くこともあります。 |
- 名前の書き方
弔事ののし紙には、水引の下中央に贈り主の名前をフルネームで書くのがマナーです。
夫婦でお供え物を贈るときは水引の下中央右側に夫のフルネームを書き、夫の名前の左側に妻の名前を書きます。
3名までの連名でお供え物を贈るときは、水引の下中央に年齢や立場が上の人を右から順番に書きます。年齢や立場に上下がないときは右からあいうえお順に書きましょう。
4名以上の場合は連名ではなく「〇〇」一同と書くのがマナー。贈った人の全員の名前を伝えたい場合は別紙に書き、お供え物に添えてお渡しします。
お仕事上のおつきあいなどで遺族の方に名前だけでは誰かなのかが分かりづらいとき、会社名や団体名、肩書などを名前の右上に小さめの文字で書きましょう。
- 表書きの文字の色
弔事ののし紙の文字を書くときには筆や筆ペンを使い、四十九日前は薄墨で書きます。
表書きに薄墨を使う理由の1つはお悔みが急で墨をしっかり用意する時間がなかったことを表すため。
薄墨を使うもう1つの理由は悲しみの涙で書いた文字が薄くなってしまったことを意味するためです。
薄墨か墨かはお供え物を贈るタイミングにより使い分けましょう。
お供え物をいただいたときのお返し

一般的に、現金であるお香典をいただいたときは必ず香典返しをします。
しかし、お供え物はいただいた方全員にお返しする必要はありません。
10,000円以上の高額な品をいただいたり、葬儀に来られなかった方からお供え物をいただいた場合はお返しが必要です。
お供え物のお返しが必要なときには、いただいた物の1/3~半額の品を当日もしくは法要後10日以内にお渡しし、掛け紙の表書きは「志」とするのが一般的です。
ここではお供え物をいただいたときのお返しについて解説していきます。
お供え物のお返しが不要なケース
お供え物にお返しが不要なケースもあります。次の2つのケースです。
- 食品、お花、お線香、ロウソクなどをいただいた場合
一般的に、現金であるお香典以外のお供え物をいただいた場合のお返しは不要です。
お供え物が食品、お花、お線香、ロウソクなどであればお返しはしなくてよいとされています。
ただし、上記の物であっても10,000円を超えるような品物であればお返しする必要があります。
- お相手がお返しを辞退された場合
お相手がお返しを辞退された場合は、お返しはしません。辞退された方にお返しをするのはかえって失礼にあたるからです。
お相手がお返しを辞退されるのは、遺族の負担を考えたり費用をかけてほしくないと思ったりして申し出ることが多いです。
また、連名でお供え物を贈った場合もお返しを辞退されることがあります。
連名の場合は1人当たりの負担が少ないため、お返しもらうほどではないと思われる方が多いからです。
どちらのケースもお返しの品は不要ですが、いただいたままにするのは失礼にあたります。
お礼状を送り、お供え物をいただいたお相手に感謝を伝えましょう。
お供え物のお返しの選び方
お供えのお返しにはいただいた金額の1/3~半額の品を選びましょう。
お供えと同じく不幸を残さないという意味を込めて食べ物や消耗品といった消え物が良いとされます。
葬儀や法要当日にお返しを渡すことも多いため、お返しには軽くてかさばらない物が選ばれることが多いです。
お返しに選ばれる代表的な物は、海苔やお菓子、日本茶などです。
お返しにはお供え物と同じように弔事ののし紙で、水引は黒白か黄白の結び切りの物を使います。
関東では黒白、関西では黄白の水引を使うことが多いようですが、地域の慣習にならった物を確認しておくと失礼がないでしょう。
お返しの表書きは水引の中央上に「志」とするのが一般的です。
「志」には感謝の気持ちをこめた心ばかりのお返しという意味があります。
名前は水引の中央下に施主の名前を書きます。施主と故人が同姓であれば苗字だけでかまいませんが、同じ苗字の同席者が多い場合はフルネームを書きます。
また、施主と故人の苗字が異なる場合には故人の苗字で「〇〇家」と入れることが多いです。
お供え物のお返しは法要後10日以内にお贈りするのが望ましいとされます。
贈り主に直接手渡しする、手渡しが難しいときはお礼状を添えて送付するのがマナー。
お返しの場合はのし掛けするとき内掛けにすると上品な印象をあたえますよ。
まとめ

- 神式のお供えには「昆布」や「干ししいたけ」、仏式のお供えには「フリーズドライのお味噌汁」や「焼き海苔」などの分けやすい乾物がおすすめ
- お供え物には「のし紙」でなく「掛け紙」を使い、表書きは「御供物」、のし掛けは外掛けにする
- お供え物のお返しには、いただいた物の1/3~半額の品を当日もしくは法要後10日以内に贈り、掛け紙の表書きは「志」とする
お供え物は、故人やご先祖さまへの感謝を込めて贈る物。
乾物は日持がし、かさばらない食べ物なのでお供え物に適しています。
神式には海の幸、山の幸の乾物、仏式では小分けされて配りやすい乾物が喜ばれます。
失礼のないようにポイントをおさえて、故人を偲ぶ機会を作ってくれた遺族の方へにも喜ばれる物を選びたいですね。
この記事を書きながら、私は亡くなったおばあちゃんのことを思い出していました。

いつも炊き立てのご飯をおばあちゃんが仏さまにお供えしていたな。
当時の記憶がよみがえり、とても懐かしい気持ちがしました。
ときには故人を思い出し、感謝を込めてお供え物すると、ご先祖さまもきっと喜ばれることでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
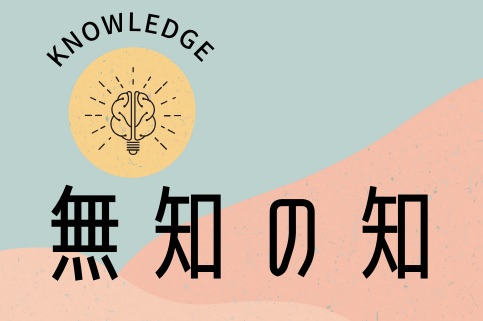

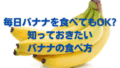

コメント